「最近インスタで見た“せいろ蒸し”、めちゃくちゃおしゃれで美味しそう…」
「でも、いざ始めようと思ったら“蒸し板”って何!?聞いてないよ…」
そんなふうに慌てて検索したあなた、もしかして私と同じで——
せいろを買ってから『使い方』に戸惑ってませんか?

せいろ買ったけど、鍋とサイズ合わなくて…蒸し板って必要なの?

うん、でも安心して!実は100均の“アレ”で代用できる場合もあるよ♪

ほんとに?100均で全部そろうなら助かるけど、ちゃんと蒸せるのかな…

実際にセリアやダイソーのグッズを使って検証してみたから、見てみて!

せいろデビューに失敗したくないあなたへ。
この記事では、100均グッズで“蒸し板”や“蒸し布”が本当に代用できるのかをリアルに比較してみました。
\ 結論はコスパ最強なのは、100均グッズで代用です /
これからせいろ蒸しを始めたい人にこそ届けたい、**お財布にも優しい「スタート術」**をお伝えします。
***************************
コーヒーとスイーツで日々の疲れを癒していきませんか!?
***************************
\ ちょっと聞いてよ、奥さん これ知ってました? /
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ひょっとして料理に興味あるけど、
スイーツはもっと興味があったりしますか?
超お得にシャトレーゼのスイーツをゲットできる秘密の方法
期間限定でシェアしてます!!

スイーツ大好きママさんは
ぜひ、覗いてみてね!!!
実質2,000円でスイーツ三昧!?ふるさと納税で手に入るシャトレーゼ特集
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
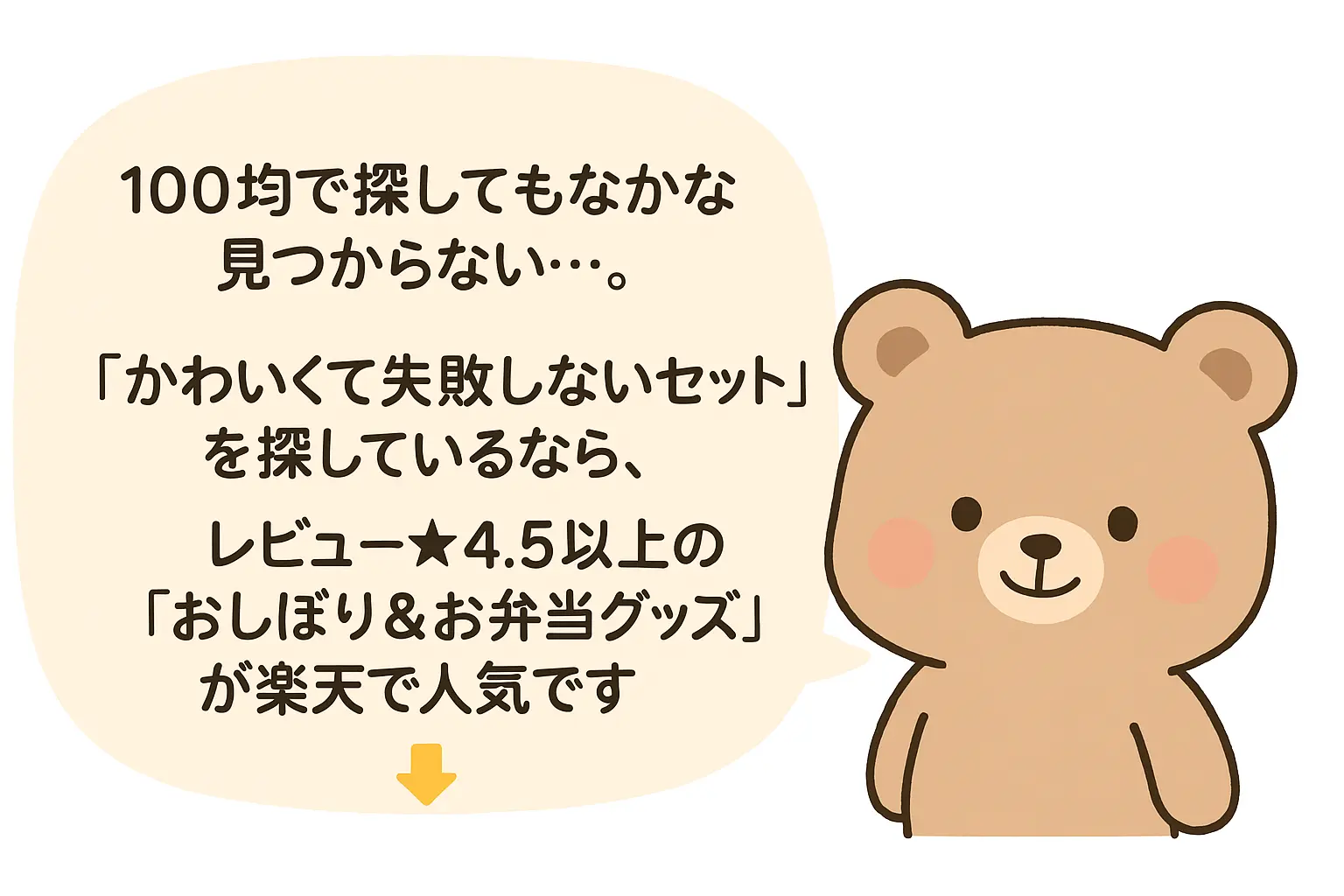
売り切れ注意のせいろをチェック!!
\ せいろ、レビュー上位ランキング商品はこちら /

「せいろに“蒸し板”ってほんとに必要?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
100均のキッチンアイテムで代用できたら、ちょっと得した気分になりますよね。
でも実際、「安定感」「蒸気の通り」「焦げ付き」など、気になるポイントはたくさん…
今回はそんな疑問にお応えすべく、3種類の道具を使ってリアルに検証してみました!
🟡 「蒸し板 vs 100均アイテム」…勝者はどっち?
結論が気になる方は、まずこちらの表をチェックしてみてください👇
| 項目 | 蒸し板(専用品) | 100均アイテム①:ステンレス網 | 100均アイテム②:鍋敷き | コメント・使用感まとめ |
|---|---|---|---|---|
| 安定感 | ◎ 高さがあり安定する | △ 若干ぐらつく | △ 湯に浸かりやすい | 蒸し板は鍋底との距離が安定する |
| サイズの自由度 | ◯ 一般的なサイズ展開 | ◎ カット可能で柔軟 | △ 固定サイズのみ | ステンレス網は調整しやすい |
| 蒸気の通りやすさ | ◎ 最適な穴配置 | ◯ 網目が細かすぎることもある | △ 底面に密着しやすい | 専用設計の蒸し板が一歩リード |
| 耐久性・劣化しにくさ | ◎ 長期間使える | △ 曲がる/サビやすい | △ 焦げ跡がつきやすい | 100均アイテムは消耗品と割り切る |
| 価格(目安) | 800円〜1500円前後 | 110円 | 110円 | コスパだけで見るなら100均が魅力 |
| 総合評価(コスパ以外含む) | ★★★★★(満足度高) | ★★★☆☆(応急用にはアリ) | ★★☆☆☆(工夫すれば可) | 「使いやすさ」なら蒸し板に軍配! |
- 蒸し板って必要?せいろ初心者が最初につまづくポイントとは
- 実際に試してみた!セリア・ダイソーの代用グッズレビュー
- 鍋とせいろのサイズ相性は?おすすめの組み合わせ早見表
- 100均だけでOK!せいろ生活スターターセット【初心者向け】
- 蒸し布・せいろの手入れはどうする?長く使うための基本ケア
- 100均の蒸し板は使える?実際に使ってわかったこと
- 蒸し布は100均で買える?セリア・ダイソーで見つけたおすすめ品と代用品
- 蒸し布を使うとどう変わる?使い方と効果
- 100均に蒸し板は売ってる?【セリア・ダイソーの実態】
- 100均せいろ蒸し板の選び方と購入場所
- せいろ蒸し板をAmazonで購入する際の注意点
- せいろ蒸し板で日本料理から中華料理まで楽しむ
- 蒸し板がなくてもせいろは使える?【代用グッズ5選】
- 100均蒸し板の耐久性と注意点【実際に使ったレビュー】
- ちゃんと使いたい人におすすめ!100均以外の蒸し板3選
蒸し板って必要?せいろ初心者が最初につまづくポイントとは
せいろ蒸しに挑戦しようと思ったとき、「蒸し板」という名前に戸惑う人は少なくありません。蒸し板とは、せいろを鍋の上に安定して置くための“台座”のような存在です。ですが、せいろを初めて買った方の多くは「蒸し板の存在を知らなかった」「せいろを鍋に直接置こうとして焦げた」など、思わぬ落とし穴に直面しています。
特にネットやSNSでせいろに憧れて購入した人ほど、「あれ?なんか思ったのと違う……」と不安になってしまうケースがあるんですね。そんなとき、100均のグッズで手軽に代用できるとしたら、ちょっと安心できると思いませんか?
蒸し板がないとせいろは使えない?初心者が知っておきたい基礎知識
蒸し板の役割は、鍋との隙間をつくり、せいろにしっかり蒸気が回るようにすること。これがないと鍋とせいろが密着しすぎてうまく蒸せなかったり、最悪の場合はせいろの底が焦げることも。とはいえ、専用の蒸し板は少し高価で、購入をためらう人も多いのが現実です。
実はこの“蒸し板の代用問題”こそ、せいろ初心者の最初の壁なんです。
100均グッズで蒸し板の代用はできる?セリア・ダイソー商品をチェック!
「蒸し板って、100均にあるの?」という疑問は非常に多いです。結論から言えば、100均の鍋敷きやステンレスラックなどを使って蒸し板の役割を果たすことは可能です。
たとえばセリアの「ステンレス鍋敷き」や、ダイソーの「脚付きトレイ」は、鍋との隙間を作りやすく、安定感もあるため代用品として活用されています。もちろん、鍋やせいろのサイズとの相性はチェックが必要ですが、うまく選べば数百円で“せいろ蒸しセット”が完成することも。
初心者がつまづきやすい“蒸し板問題”、100均グッズでどこまでカバーできるか、実際の比較を通して見ていきましょう。
実際に試してみた!セリア・ダイソーの代用グッズレビュー
100均で売られている「蒸し板の代用品」が本当に使えるのか、実際に使ってみました。写真は割愛しますが、手元にある鍋とせいろに合わせて、以下の2商品を試しています。
セリア|ステンレス製鍋敷き(脚付きタイプ)
価格:110円(税込)
サイズ:直径約16cm(複数サイズあり)
素材:ステンレス製、脚付きタイプ(高さ約1.5cm)
良かった点:
-
脚がしっかりしていて、せいろを安定して乗せられる
-
鍋底とせいろの間にしっかり蒸気の通り道ができた
-
ステンレス製なので熱にも強く、洗いやすい
気になった点:
-
鍋より鍋敷きが大きいと不安定になる(鍋との相性要注意)
-
鍋底がフラットでないとガタつく可能性あり
総合評価: 初心者の“お試し用”としては十分すぎる性能。
ダイソー|脚付き焼き網トレイ(丸型)
価格:110円(税込)
サイズ:直径約19cm(複数サイズあり)
素材:スチール製、脚付き(高さ約2cm)
良かった点:
-
鍋のサイズに合えば、ぴったりフィットして動きにくい
-
蒸し布も上にかけやすく、蒸気が全体に回りやすい構造
-
コスパ最強。実質“蒸し板”として十分使える
気になった点:
-
網状なので、せいろの脚がズレやすい場合がある
-
長期使用だとスチール部分が劣化する可能性あり
総合評価: サイズが合えば、100均の神アイテムとして活躍!
このように、100均アイテムでもちょっとした工夫とサイズ確認さえすれば、専用の蒸し板と同じくらいの働きをしてくれることが多いんです。
鍋とせいろのサイズ相性は?おすすめの組み合わせ早見表
せいろと鍋を組み合わせるときにもっとも大事なのが「サイズの相性」です。鍋が小さすぎると不安定になり、せいろがうまく置けなかったり、蒸気が回らない原因にもなります。逆に、鍋が大きすぎてもせいろが沈み込んでしまい、焦げつきやすくなります。
そこで、下記の早見表を参考にして、あなたのせいろサイズに合った鍋の大きさを確認してみましょう。
| せいろのサイズ(外径) | 推奨される鍋の内径 | コメント |
|---|---|---|
| 15cm(1~2人用) | 約12〜13cm | 小型鍋・一人暮らし向き |
| 18cm(2人前) | 約15〜16cm | よくある家庭用片手鍋に合いやすい |
| 21cm(2~3人用) | 約18〜19cm | 汁鍋や両手鍋サイズがベスト |
| 24cm(3~4人用) | 約21〜22cm | 安定感があり、大きめ鍋が必要 |
| 27cm以上(4人以上) | 約24cm以上 | 土鍋・中華鍋との組み合わせ推奨 |
ポイント: 鍋の内径は、せいろより「2〜3cm小さい」サイズがベスト。これにより、せいろが鍋にしっかり乗り、蒸気の逃げ道も確保できます。
100均だけでOK!せいろ生活スターターセット【初心者向け】
| アイテム | おすすめ商品 | 備考 |
| 蒸し板代用品 | ステンレス鍋敷き(セリア)/脚付き網(ダイソー) | 鍋とのサイズ確認が必須 |
| 蒸し布(クッキングクロス) | キッチンクロス(キャンドゥ等) | 木綿素材推奨・目が粗すぎないもの |
| ミトン・トング | シリコンミトン(セリア)/トング(ダイソー) | 火傷防止の必需品 |
| 下に敷く水受けトレイ | 耐熱皿や鍋敷き | 水滴対策&テーブル保護用 |
蒸し布・せいろの手入れはどうする?長く使うための基本ケア
▶ 蒸し布の洗い方
-
使用後すぐに水で洗い、汚れを軽く落とす
-
中性洗剤で手洗い or ネットに入れて洗濯機へ
-
乾燥機NG!自然乾燥が基本です
▶ せいろ本体の手入れ方法
-
洗剤は使わず、水洗い&乾拭き
-
風通しの良い場所でしっかり乾燥させる
-
カビ防止のため、密閉保管は避ける
🧺 おすすめ代用品:セリアの木製まな板立てを乾燥スタンドとして活用すると便利!
100均の蒸し板は使える?実際に使ってわかったこと

最近「せいろ調理」が注目されている中で、「蒸し板って必要?」「100均のもので代用できないかな?」という声をよく見かけます。
私自身も、なるべくお金をかけずにせいろを使いたかったので、セリア・ダイソー・キャンドゥをいろいろ回って蒸し板を探してみました。
この記事では、実際に100均で買った蒸し板を使った感想、サイズ感の注意点、そして**「蒸し板がないときの代用品」**についても紹介しています。
「これからせいろデビューしたいけど、道具選びで迷っている方」に、少しでもヒントになれば嬉しいです。
蒸し布は100均で買える?セリア・ダイソーで見つけたおすすめ品と代用品
セリア・ダイソーで見つけた「蒸し布」の実態
100円ショップで「蒸し布」という名前そのままの商品を見つけるのは、意外と難しいものです。セリアやダイソーの調理コーナーをいくつか見て回ったところ、「蒸し布」と明記された商品は見つからず、代わりに目についたのがガーゼ素材のふきんや不織布タイプのクッキングペーパーでした。
特にセリアで購入した「くっつきにくいクッキングペーパー」は、食材がせいろに貼り付かず、蒸し上がりもきれい。ダイソーでは「油こし用ペーパー」や「レンジ蒸しシート」なども候補になります。
実際に使用してみて感じたのは、「専用品でなくても、十分代用できる」ということ。ふきんタイプは洗って再利用もできるので、コスパ重視派にはありがたい存在です。
蒸し布が売ってないときの代用アイテム5選
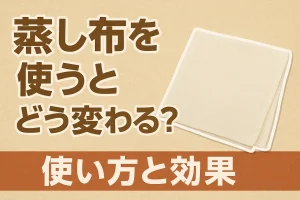
「蒸し布が見つからない」「できれば身近なもので代用したい」——そんなときに活躍する、手軽な代用品を5つご紹介します。
-
割り箸+耐熱皿 数本の割り箸を鍋底に並べて、その上に耐熱皿を乗せることで、蒸気を通すための土台に。通気性と高さを確保でき、軽い食材であればしっかり蒸せます。
-
クッキングシート セリアやダイソーで手に入る「くっつきにくいタイプ」がおすすめ。せいろの底に敷くだけで、洗い物の手間も減ります。
-
レタスやキャベツの葉 蒸すと野菜の風味がほんのり移り、見た目もナチュラル。使い終わったらそのまま食べられるのも◎。
-
ガーゼふきん ダイソーやキャンドゥで購入可能。サイズに応じてカットして使えるため、繰り返し使いたい方に。
-
ステンレス製丸網 「蒸し布」ではありませんが、直接食材が触れにくくなり、蒸気の循環も良好。高さを調整したいときに便利です。
どの代用品にも一長一短ありますが、**「通気性・安定性・素材との相性」**を意識すると、上手に代用できます。
蒸し布を使うとどう変わる?使い方と効果
蒸し布を使う最大のメリットは、食材がせいろにくっつきにくくなることです。特にシュウマイや肉まんなどの点心類は、直接せいろに置いてしまうと皮が張り付いて崩れてしまうことがありますが、蒸し布を一枚敷くだけでその心配がなくなります。
また、蒸気の循環を妨げないため、蒸しムラが起こりにくいというのもポイント。全体にふんわりとした火の入り方ができるので、見た目も美しく仕上がるのが嬉しいところです。
さらに、蒸し終わった後のお手入れも楽になります。食材のカスや油分がせいろに直接付着するのを防いでくれるので、洗う回数を減らしたい人や、せいろを長持ちさせたい人にもおすすめです。
せいろ蒸し板とは?素材と種類
せいろ蒸し板とは、鍋やフライパンの上にせいろを安定して置くための土台です。蒸気の通り道を確保しつつ、せいろをしっかり支えてくれる、いわば「縁の下の力持ち」的な存在。
素材によって特徴が異なり、主に以下の3タイプがあります。
-
木製タイプ:熱をやわらかく通す性質があり、せいろとの相性が抜群。風合いもナチュラルで人気ですが、水分に弱く、カビに注意が必要です。
-
竹製タイプ:軽量で扱いやすく、価格も手頃。木製よりも通気性に優れていますが、やはり水気には注意が必要です。
-
ステンレス製タイプ:耐久性が高く、メンテナンスも簡単。ただし、鍋とのサイズ調整が難しいこともあるため、購入前に確認が必要です。
どの素材にも一長一短がありますが、使う頻度や好みに合わせて選ぶのがポイントです。特に初心者の方は、お試し感覚で竹や木製から始めてみるのもおすすめですよ。
せいろに最適なサイズの選び方
世界のスパイスを使った料理一覧
100均に蒸し板は売ってる?【セリア・ダイソーの実態】
\こちらが実際に購入した蒸し板の写真です!/

「100均でせいろ用の蒸し板って買えるの?」という疑問は、せいろを初めて使う方にとって非常に気になるポイントですよね。実際にセリアとダイソーを何店舗か回って調査したところ、はっきりと「蒸し板」として売られている商品は見当たりませんでした。
ただし、それに近い役割を果たせるアイテムは意外と多く存在しています。たとえば、セリアにはステンレス製の丸網があり、鍋やフライパンの底に敷くことで蒸気を通す台として活用可能。**ダイソーでは「焼き網」や「レンジ蒸しプレート」**が、せいろと一緒に使う道具として代用できます。
スタッフの方に聞いてみたところ、「蒸し板の専用品はありませんが、みなさん工夫して代用してますよ」とのこと。つまり、100均には専用商品はないけれど、代用品は豊富にそろっているというのが現実です。
重要なのは、「高さ」と「安定感」のあるアイテムを選ぶこと。蒸気がしっかり循環するよう、底がフラットで熱に強い素材であるかどうかも確認するとよいでしょう。

暮らしをもっと快適にする100均グッズは、実はキッチン以外にもたくさんあります。
セリアやダイソーをフル活用して、春夏の家時間を快適に過ごすアイデアを総まとめにした記事はこちら👇
【春夏向け】100均グッズで暮らし快適!セリア&ダイソー便利アイテム総まとめ
「こんな使い方もあったのか!」という発見がきっと見つかります。
100均せいろ蒸し板の選び方と購入場所

100均ショップでせいろ蒸し板の代用品を探す際に大切なのは、「サイズの相性」と「使用環境に合った素材選び」です。せいろ本体の直径や使う鍋の大きさを事前に測っておくことで、失敗しづらくなります。
【選び方のポイント】
-
せいろと鍋のサイズをチェック
鍋の内径より小さすぎると蒸し板が不安定になります。理想は、鍋の口とほぼ同じかやや小さめサイズの蒸し板。 -
素材の特性を理解する
竹製は軽量で扱いやすいですが、濡れたままだとカビの原因になるため注意が必要。ステンレス製は耐久性が高くお手入れも簡単です。 -
高さのある構造を選ぶ
鍋底とせいろの間に1~2cm程度の蒸気スペースができるものを選ぶと、蒸しムラが起きにくくなります。
【購入できる主な場所】
-
ダイソー:焼き網や金属製の小さなプレート、丸網などがせいろ用に使えそうなラインナップ。
-
セリア:不織布や竹製の敷物、耐熱トレイが候補になります。
-
キャンドゥ:比較的キッチン雑貨のバリエーションが豊富で、小型せいろと併せて使える道具も探しやすいです。
注意点として、店舗ごとに在庫や取り扱い商品が異なるため、**「一度で見つからなくても複数店舗を見て回るのがおすすめ」**です。また、店頭で迷ったときは、スマホで自分のせいろや鍋のサイズメモを見返しながら選ぶと安心です。
ダイソー・セリア・スリーコインズでの購入情報
100均ショップでせいろ用の蒸し板や代用品を探す場合、各店舗によって置いてある商品のラインナップや特徴に違いがあります。ここでは、実際に訪れた3つのショップでの発見や注目ポイントをまとめました。
【ダイソー】
ダイソーはキッチン用品の品揃えが非常に豊富です。店舗によっては、調理コーナーに「ステンレス丸網」や「焼き網」「プレート型トレイ」などが置かれており、どれもせいろ蒸し板の代用品として十分に使えるクオリティ。特に「脚付き焼き網」は、高さを確保できるため非常に便利です。
【セリア】
セリアでは「竹製鍋敷き」「ステンレス網」「シリコンマット」など、軽くて扱いやすいアイテムが目立ちます。せいろと一緒に使うなら、鍋敷きをひっくり返して高さを出す方法や、不織布タイプのクッキングペーパーと組み合わせて活用するのもおすすめです。特に小さめサイズのアイテムが揃っているので、一人暮らしや少量調理にも向いています。
【スリーコインズ】
300円均一ショップとして人気のスリーコインズは、デザイン性の高いキッチンアイテムが充実しています。以前は「コンパクトせいろ」本体も取り扱われており、それに対応するサイズの「蒸し台」や「ステンレス網」も陳列されていたことがあります。時期や店舗によって取り扱いにばらつきがありますが、チェックする価値はあります。
店舗選びのポイント
-
キッチン用品売り場の「焼き網」「鍋敷き」「調理プレート」コーナーを中心に探す。
-
店員さんに「せいろや蒸し料理に使える台はありますか?」と声をかけてみる。
-
季節やキャンペーン時に、せいろ調理特集コーナーが設置されることもある。
せいろを買ったものの「台がない…!」と困る前に、まずはお近くの100均でチェックしてみてくださいね。
ニトリや無印と迷ったときの比較ポイント
せいろ蒸し板をどこで買うか迷ったとき、よく候補に挙がるのがニトリや無印良品です。実際、これらの店舗ではしっかりした素材と使い勝手のよさを兼ね備えたアイテムがそろっています。
-
無印良品の蒸し板は、木製で質感が良く、見た目もナチュラルな仕上がり。耐久性が高く、長期間使いたい人にはおすすめです。
-
ニトリでは、ステンレスやアルミ製のシンプルな蒸し器台が中心。価格が控えめで、普段使いとして気軽に手に取れるのが魅力です。
比較ポイントとしては、以下のような観点で選ぶと良いでしょう:
| 比較項目 | 無印良品 | ニトリ |
|---|---|---|
| 見た目 | おしゃれで統一感がある | シンプルで実用的 |
| 素材 | 木製中心 | ステンレス・アルミ系が主流 |
| 価格帯 | やや高め(1,000円前後) | 手ごろ(500円〜800円台) |
| 耐久性 | 高め | 標準的 |
どちらも100均よりは価格が高いですが、長く使いたい方にはコスパのよい選択になることも。見た目を重視するなら無印、コスパと汎用性を重視するならニトリ、と目的別に選ぶのがベストです。
せいろ蒸し板をAmazonで購入する際の注意点
1. サイズの確認
せいろ蒸し板は、使用する鍋やせいろのサイズに合ったものを選ぶことが重要です。例えば、照宝の蒸し板セットには24cmや30cmなどのサイズがあります。購入前に、手持ちの鍋やせいろの直径を測り、適切なサイズの蒸し板を選びましょう。
2. 素材の選択
蒸し板の素材には、木製やステンレス製などがあります。木製の蒸し板は、自然な風合いで食材に香りを加えることができますが、手入れが必要です。一方、ステンレス製の蒸し板は、耐久性があり、手入れが簡単です。使用目的や好みに応じて、適切な素材を選びましょう。
3. セット内容の確認
Amazonでは、せいろ本体と蒸し板がセットになっている商品や、単品で販売されている商品があります。購入する際には、必要な部品がすべて含まれているかを確認しましょう。例えば、照宝の蒸し板セットには、せいろ本体と蒸し板が含まれています。
4. 商品説明とレビューの確認
商品の説明やレビューを確認することで、実際の使用感や品質を把握することができます。特に、サイズ感や耐久性、使い勝手などの情報は、購入の参考になります。また、商品の写真や詳細情報も確認し、納得のいく商品を選びましょう。
これらのポイントを参考に、Amazonでのせいろ蒸し板の購入を検討してみてください。適切な商品を選ぶことで、蒸し料理をより楽しむことができます。
せいろ蒸し板のサイズ選びと対応フライパン
せいろ蒸し板を選ぶときに見落としがちなのが、「自宅で使う鍋やフライパンとの相性」です。
せいろの直径だけで選ぶと、鍋やフライパンの口径と微妙に合わず、蒸気が漏れたり、せいろが安定しなかったりすることもあります。たとえば、18cmのせいろを使いたいなら、鍋の内径はせいろよりもやや小さめ(16〜17cm)であるとしっかりフィットしやすくなります。
一方で、家庭用のせいろとして人気のある21cmサイズは、3〜4人分の料理にも対応しやすく、汎用性が高いです。ただし、フライパンによっては22cm以上ないと安定しないこともあるので注意が必要です。
また、フライパンの素材や形状もポイント。底がフラットなものの方がせいろ蒸し板を安定して置けるため、熱伝導がスムーズになります。逆に、丸底タイプや縁が高すぎる鍋はせいろが不安定になる原因になるので、あらかじめ調理器具の形状も確認しておくと安心です。
ちょっとしたサイズの差が使いやすさに直結するため、せいろと一緒に「どの鍋・どのフライパンに乗せるか?」という視点も忘れずにチェックしておきましょう。
中華用せいろ蒸し板と家庭用サイズの違い
せいろ蒸し板には、中華料理店などで使われる業務用サイズと、家庭向けの小型サイズがあります。この違いを把握しておくことで、自分の目的に合ったものを選びやすくなります。
中華料理店でよく使われるせいろは、直径が30cm以上の大型サイズが中心です。一度にたくさんの食材を蒸せるため、大量調理に向いていますが、自宅のキッチンやコンロには大きすぎることも。
一方、家庭用のせいろ蒸し板は15〜21cm程度のサイズが主流で、収納にも困らず取り回しがしやすいのが魅力。2〜4人分の調理にはこれで十分対応できます。特に、21cmサイズはバランスが良く、初心者から料理好きの方まで幅広く支持されています。
さらに、中華用の蒸し板は業務用鍋とセットで使うことを前提に作られているため、鍋の形状や火力にも対応できる設計になっています。その分重くて厚みがあるため、家庭用のコンロやフライパンとは相性が悪いことも。
そのため、家庭で気軽にせいろ料理を楽しみたいなら、小型で扱いやすい家庭用サイズを選ぶのがおすすめ。逆に、大人数でのパーティー料理や本格的な中華料理を作る予定がある場合は、中華用サイズを検討しても良いでしょう。
100均せいろ蒸し板の使い方と必要な道具
100均で手に入るせいろ蒸し板は、手軽にせいろ調理を始めたい人にとって心強いアイテムです。けれども、うまく使いこなすにはちょっとしたコツと準備が必要です。
まずは基本の使い方。鍋やフライパンの上に蒸し板を置き、その上にせいろを重ねます。鍋の中にはあらかじめ1〜2cmほど水を入れておき、沸騰させることで蒸気を発生させます。蒸し板はその蒸気をせいろに届ける橋渡しのような役割を果たすため、鍋との相性がとても重要になります。
必要な道具は以下の通り:
-
蒸し板(100均やキッチン用品店で購入可)
-
鍋またはフライパン(蒸し板が安定して置けるサイズ)
-
蒸し布またはクッキングシート(食材がくっつくのを防ぐ)
-
トングや菜箸(取り出しやすく火傷防止に便利)
特に注意したいのが蒸し板と鍋のサイズ感。100均の蒸し板はサイズが限られているため、家庭にある鍋としっかり合うかどうかを事前に確認しましょう。合わない場合は、蒸し板の下にアルミホイルなどを巻いて高さを調整することもできます。
また、水の量にも気を配ること。水が多すぎると蒸し板やせいろの底に直接触れてしまい、食材がベチャつく原因に。逆に少なすぎると途中で空焚きになるリスクがあるので、火をつける前にしっかり確認を。
こうした準備と使い方を押さえるだけで、100均の道具でもしっかり美味しい蒸し料理を楽しむことができますよ。
蒸し板と蒸籠のセットアップ方法
せいろ蒸し板を鍋やフライパンの上にセットし、その上にせいろを置くことで、蒸気をしっかりと行き渡らせることができます。適切にセットアップすることで、均一に蒸気が行き渡り、食材の美味しさを最大限に引き出せます。
まず、鍋のサイズに合ったせいろ蒸し板を選ぶことが重要です。鍋の直径とせいろ蒸し板のサイズが合わないと、蒸気が逃げやすくなり、食材がうまく蒸されません。使用する鍋が大きすぎる場合は、隙間を埋めるための布巾やアルミホイルを使うと、蒸気の流れを整えることができます。
次に、鍋の底に適量の水を入れます。水が多すぎるとせいろの底が濡れてしまい、食材がべちゃっとした仕上がりになってしまうため、適度な量を守ることがポイントです。一般的には、鍋の底からせいろの底まで1〜2cmの隙間を保つのが理想的です。
さらに、せいろ蒸し板を設置した後、蒸し布やクッキングシートを敷くことで、蒸し板の汚れを防ぎ、後片付けを簡単にすることができます。蒸し布を使うことで、蒸気が食材に均一に行き渡りやすくなり、ふっくらとした仕上がりになります。また、布の代わりに野菜の葉(キャベツや白菜)を敷くと、より香り豊かな蒸し料理を楽しめます。
最後に、火加減にも注意が必要です。最初は強火で一気に蒸気を発生させ、その後中火〜弱火に調整しながら蒸すと、食材がふんわり仕上がります。蒸し時間も料理ごとに異なるため、目安時間を確認しながら調理するとよいでしょう。
点心・肉まんを美味しく蒸すためのコツ
せいろで点心や肉まんを美味しく仕上げるには、いくつかの「ちょっとした工夫」が効果的です。
まず大切なのが敷き紙や蒸し布の活用です。シュウマイや肉まんは、蒸している間に生地がせいろの底にくっつきやすいため、クッキングシートや蒸し布を使うことで、見た目も崩れずキレイに仕上がります。100均で買えるクッキングシートでも十分代用可能なので、手軽に準備できます。
次に気を付けたいのが配置の仕方。食材同士がくっつかないように間隔をあけて並べることで、蒸気の通り道ができて全体が均等に蒸し上がります。とくに肉まんは膨らむため、少し余裕を持たせて並べるのがポイントです。
さらに仕上がりをふっくらさせるためには、蒸す前に霧吹きで軽く水をかけるのもおすすめ。皮の乾燥を防ぐことで、しっとりジューシーな仕上がりになります。
そして火加減にも工夫を。最初は強火でしっかり蒸気を立てて、途中から中火〜弱火に落としてじっくり蒸すと、ムラのないふわふわ食感になります。
ちょっとしたコツの積み重ねが、仕上がりの美味しさに直結するのがせいろ調理の面白さ。ぜひ自宅で気軽に点心づくりを楽しんでくださいね。
専用シートや用紙の使い方でお手入れを簡単に
蒸し料理を手軽に楽しむうえで、**「後片付けのラクさ」**は意外と大事なポイント。そんなときに活躍してくれるのが、クッキングシートや専用の蒸し紙といった便利アイテムです。
せいろや蒸し板に直接食材を乗せると、調理後に焦げつきや汚れが残りやすく、洗う手間もかかります。ですが、シートを敷くだけで汚れの付着をかなり軽減できるため、日常使いにもぴったり。特に、肉や魚など油分を多く含む食材では、シートがあると後始末のストレスがぐっと減ります。
また、クッキングシートは汎用性が高く、好きなサイズにカットして使えるのも便利。最近では、せいろの形に合わせた**「穴あきタイプの蒸し専用シート」**も100均で購入できるので、より本格的な蒸し調理に対応できます。
大切なのは、「蒸気がしっかり通る素材を選ぶこと」。耐熱温度と通気性のバランスを考えて、用途に合わせてシートを使い分けることで、せいろ調理の快適さはさらにアップします。
せいろ蒸し板のおすすめ料理とヘルシーメニュー
せいろを使った料理は、油を使わずに調理できるため、健康を気遣う方にもぴったりです。とくにおすすめなのが、野菜たっぷりの蒸し料理。にんじんやブロッコリー、カボチャなどをカットして並べ、蒸し時間を調整するだけで、素材の甘みがぐっと引き立ちます。
また、肉や魚の蒸し物も、せいろならふっくらジューシーに仕上がります。鶏むね肉や鮭を野菜と一緒に蒸すことで、ヘルシーかつボリュームのある一皿に。さらに、ポン酢やごまだれ、柚子胡椒などの和風ソースを添えると、飽きずに食べられます。
手軽さを重視するなら、冷凍肉まんやシュウマイの温め直しにもせいろは最適。電子レンジとは違い、水分を保ったまま温められるため、まるでできたてのような食感を楽しめます。
せいろ蒸し板は、和食・中華問わず幅広い料理に応用が効き、食卓に健康と華やかさをプラスしてくれる存在です。
手軽に作れる野菜たっぷりのせいろ蒸しレシピ
せいろで蒸した野菜は栄養価が高く、ダイエットにもおすすめです。キャベツやニンジン、ブロッコリーなどを一緒に蒸して、ポン酢やゴマダレでいただくと美味しくなります。さらに、カボチャやサツマイモを加えると甘みが増し、お子様にも食べやすくなります。蒸し時間を工夫することで、シャキシャキとした食感を楽しむこともできます。
また、シンプルな塩やオリーブオイルをかけるだけでも素材の甘みを引き出すことができます。さらに、香ばしいゴマやナッツをトッピングすれば、食感のアクセントにもなり、栄養価もアップします。タレには、ポン酢におろしショウガやニンニクを加えると、より深みのある味わいに仕上がります。
ヘルシーで美味しい点心や肉まんの調理法
100均のせいろ蒸し板を使えば、市販の点心や冷凍肉まんも手軽にふっくら蒸しあげることができます。特に肉まんは、電子レンジとは違い、せいろで蒸すことで皮がしっとりと柔らかく仕上がり、中の餡もジューシーに感じられます。
蒸すときは、クッキングシートやキャベツの葉を敷いておくと、くっつきを防ぎつつ後片付けもラクになります。せいろに並べるときは、間隔を空けることで蒸気の通り道ができ、仕上がりがより均一になります。
また、手作りのシュウマイや餃子をせいろで蒸すのもおすすめです。皮のもちっとした食感と、中の具材のジューシーさが際立ち、蒸したてならではの美味しさが楽しめます。エビや椎茸、タケノコなどを加えてアレンジすれば、家庭でも本格中華が味わえます。
忙しい日のランチにもぴったりな蒸し点心。冷凍保存しておけば、食べたいときに蒸すだけでできたての味が楽しめるので、常備しておくと重宝します。
蒸し板を使ったプレート料理の応用アイデア
蒸し料理をもっと楽しむ方法として、プレートランチ風にアレンジするのもおすすめです。せいろで蒸した食材をそのまま食卓に並べるだけで、見た目も華やかで特別感のある一皿が完成します。
たとえば、カラフルな野菜を中心にした「せいろ野菜プレート」なら、蒸し野菜にポン酢やごまだれ、岩塩などのソースを添えて、味のバリエーションを楽しむことができます。ワンプレートスタイルにすれば洗い物も少なく済むため、忙しい日にもぴったり。
また、「蒸し鶏プレート」も手軽で栄養バランスの良い一品。鶏むね肉やささみをせいろで蒸し、ゆで卵や葉野菜と一緒に盛り付けることで、タンパク質もたっぷり取れます。おにぎりやパンと組み合わせれば、和風・洋風どちらにもアレンジ可能。
ちょっとした工夫で、せいろ=蒸すだけの道具というイメージを超えた、おしゃれで満足感のある食卓が完成します。特別な日や来客時にも活躍するスタイルなので、ぜひ挑戦してみてください。
せいろ蒸し板で日本料理から中華料理まで楽しむ
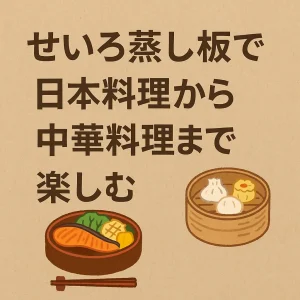
せいろ蒸し板は、日本料理にも中華料理にも幅広く対応できる万能調理アイテムです。伝統的な和の蒸し物から本格的な点心まで、自宅で簡単に再現できるのが魅力です。
たとえば、和食で人気の「茶碗蒸し」や「ふろふき大根」は、せいろを使うことで、優しい火の通りとしっとりとした仕上がりが叶います。蒸気でじっくり加熱することで、素材の旨みが凝縮され、見た目も美しくなります。
一方、中華料理では「小籠包」や「エビ餃子」などが定番。せいろを使えば、蒸気が全体にしっかりと行き渡り、皮がもちもちでジューシーな仕上がりに。市販の冷凍点心でも、せいろで蒸すだけでお店のような本格的な味わいになります。
また、せいろはそのままテーブルに出せる見た目の美しさもポイント。蒸し板を使って調理すれば、安定感もあり、せいろの扱いがスムーズに。和食・中華問わず、家庭の食卓をワンランクアップさせてくれるアイテムです。
蒸し板を使った日本伝統の蒸し料理
せいろ蒸し板は、和の食卓にもなじみ深い調理法をより手軽に実現してくれる存在です。特に、茶碗蒸しやふろふき大根、蒸し寿司といった日本の伝統的な蒸し料理には欠かせません。
たとえば、茶碗蒸しは出汁の風味を大切にしながら、卵液をなめらかに蒸し上げるために、蒸気の強さと均一な加熱が重要です。蒸し板を使えば、鍋やフライパンの上にせいろを安定して設置でき、穏やかな蒸気で優しく火が通るため、失敗が少なくなります。
ふろふき大根も、あらかじめ出汁で煮てからせいろで仕上げることで、余分な水分が飛び、大根の甘みがぎゅっと凝縮されたような食感になります。みそだれをかけて提供すれば、おもてなし料理にもぴったりの一品に。
また、蒸し寿司は酢飯と具材をせいろに並べて温めるだけで、ほんのり温かく香り高い仕上がりに。蒸すことで酢の角が取れ、まろやかな味わいになります。冷たくなりがちな酢飯に、ひと手間の“温もり”を加えることができるのが、せいろ調理ならではの魅力です。
これらの料理は、一見手間がかかりそうに見えて、蒸し板とせいろさえあれば意外と手軽に挑戦できます。どこか懐かしく、ほっとする味わいを、ご家庭でもぜひ楽しんでみてください。
中華風点心の調理と盛り付けアイデア
せいろ蒸し板を使えば、自宅でも本格的な中華点心の調理が可能になります。シュウマイ、小籠包、春巻き、餃子など、中華の定番メニューをせいろで蒸すことで、外はもっちり、中はジューシーに仕上がり、蒸したてならではの美味しさを味わえます。
まず調理のポイントとしては、点心をせいろに並べる際に間隔を空けること。蒸気がしっかりと行き渡り、均等に火が通るため、仕上がりがふっくらとします。下にクッキングシートや専用の蒸し紙を敷いておけば、皮がくっつくのを防ぎ、せいろの汚れも最小限に抑えられます。
さらに、盛り付けのひと工夫でテーブルの雰囲気がぐっとアップします。せいろごと食卓に出すことで、本格的な飲茶スタイルを演出でき、まるで中華レストランにいるような気分に。点心の隣に青菜やミニトマト、香菜(パクチー)などの彩り野菜を添えれば、視覚的にも華やかになります。
ソースも複数用意すると味の幅が広がります。定番の酢醤油やラー油だけでなく、柚子胡椒、黒酢、ごまダレなどを小皿に分けて並べると、お店のような特別感が出せます。
点心の美味しさは、見た目や香り、湯気とともに楽しむ“体験”そのもの。せいろと蒸し板があれば、その魅力を家庭でも十分に再現できます。週末のブランチや来客のおもてなしにもぴったりです。
おしゃれな蒸し料理のプレゼンテーション
せいろ料理の魅力は、味や栄養だけでなく「見た目」でも楽しめる点にあります。ふたを開けた瞬間に立ち上る湯気とともに、彩り豊かな野菜や点心が並ぶ光景は、それだけで食卓に華やかさを添えてくれます。
まずおすすめなのが、せいろをそのまま食卓に出すスタイル。ナチュラルな木目とほのかな木の香りが、食事の時間に温かみをプラスします。竹や木製のトレイの上にせいろを置いたり、和風のランチョンマットと合わせたりすることで、カフェ風のコーディネートが完成します。
さらに、蒸した料理をプレートや大皿に移し、アレンジを加える方法もおすすめです。野菜を放射状に並べたり、小さな器でソースを添えたりするだけで、一気にプロのような仕上がりに。ハーブやエディブルフラワーを添えると、季節感も演出できます。
特に来客時や特別な日の食事では、せいろごとテーブルに並べるだけで話題に。湯気とともに料理が提供されることで、視覚・嗅覚・味覚すべてで楽しめる演出になります。蒸し料理は“地味”と思われがちですが、盛り付けと演出次第で一気に垢抜けた食卓を作れるのが魅力です。
蒸し板がなくてもせいろは使える?【代用グッズ5選】
まずは、身近なアイテムで蒸し板の代用ができる方法をご紹介します。
\こちらが「割り箸+お皿」で代用した蒸し板の例です/

「せいろを買ったけど、蒸し板がない!」そんなときも大丈夫。実は身近なもので代用できるアイテムがいくつかあります。特に100均や家にあるもので代用できると、手軽にせいろ調理をスタートできます。ここでは、筆者が実際に試してみて役立った代用品を5つ紹介します。
1. 割り箸を敷く方法
鍋の底に割り箸を数本並べて、その上にせいろを乗せるシンプルな方法。安定感にはやや欠けますが、軽い食材なら問題なく使えます。
2. 耐熱皿を裏返す
平らな耐熱皿を逆さにして鍋にセットすることで、蒸気がせいろにしっかり届く台座になります。鍋のサイズと皿のバランスに注意すれば、安定性もありおすすめです。
3. ステンレス製の丸網
100均でも販売されている丸網は、蒸し板の代用品として定番。通気性が良く、せいろをしっかり支えてくれる点も安心です。
4. 鍋のフタを逆さに置く
意外と便利なのが、鍋のフタを裏返して使う方法。ドーム型であれば、中央が盛り上がっている分、せいろが安定して乗せやすくなります。
5. 焼き網を活用
カセットコンロ用の焼き網なども、鍋のサイズに合えば代用可能。こちらもステンレス製が多く、耐久性にも優れています。
いずれも「高さ」「安定性」「通気性」がポイント。重たい食材を蒸す場合は特に安定感を優先しましょう。せいろを気軽に試したい方は、まずは家にあるもので代用してみるのもおすすめです。
簡単に作れる100均せいろ蒸しメニュー
せいろを使った調理というと、手間がかかりそうなイメージがありますが、実はとてもシンプル。特に100均のせいろや蒸し板を活用すれば、身近な食材で手軽に美味しい蒸し料理が楽しめます。ここでは、初心者でも失敗しにくい、簡単にできるおすすめのせいろレシピを3つご紹介します。
1. カラフル野菜のせいろ蒸し
ブロッコリー、にんじん、パプリカ、アスパラなど、彩りの良い野菜を一口大に切ってせいろに並べるだけ。蒸気でしっかり火を通すことで、野菜の自然な甘みが引き立ちます。仕上げにポン酢や塩、ごまだれを添えると、シンプルながら飽きのこない一品になります。
2. 冷凍肉まんのふわふわ蒸し
コンビニやスーパーで売られている冷凍肉まんをそのまませいろで蒸すだけで、皮はふんわり、中はアツアツの本格的な仕上がりに。蒸す前にクッキングシートを敷いておけば、くっつきも防げて後片付けもラク。電子レンジより美味しく仕上がるので、ぜひ試してほしいメニューです。
3. おしゃれな市販シュウマイの温め直し
市販の冷凍シュウマイやチルド商品も、せいろで蒸し直すだけで本格的な味に大変身。せいろに小さな耐熱皿を並べて盛り付ければ、おしゃれなワンプレート感覚で楽しめます。仕上げにネギやカラシ、ポン酢を添えると、お店のような雰囲気が出て特別感もアップ。
どれも短時間で作れて、準備や片付けも簡単。冷蔵庫の残り野菜やストック食材を活用すれば、日常使いにぴったりな蒸しメニューになります。まずはお気に入りの一品から、気軽にせいろ調理を楽しんでみてください。
100均で揃う「せいろ蒸しをもっと楽しむアイテム」
- 蒸し布(食材がくっつくのを防ぐ)
- 小さめの竹トング(取り出しやすい&おしゃれ)
- スパイス&調味料(塩レモン、ハーブソルトで洋風蒸し)
- カフェ風小皿(おしゃれな盛り付けに)
せいろのスタイリング&テーブルコーディネート
- テーブルにそのまま出すと映える!
- 木のプレートにせいろをのせる
- 和モダン風の器やランチョンマットを使う
- 蒸し料理を組み合わせると豪華なワンプレートに
- せいろ蒸し+おにぎり+味噌汁でカフェ風和食
- せいろ蒸し+バゲット+チーズで洋風アレンジ
100均せいろ蒸しで意外と知られていない裏ワザ!
せいろ蒸しはシンプルな調理方法ですが、ちょっとした工夫でさらに美味しく、便利に使えます。
- お湯を先に沸かしてから蒸すと時短に!
- せいろに食材をセットしてから火をつけるのではなく、事前にお湯を沸騰させておくと蒸し時間を短縮できます。
- 蒸し布の代わりにクッキングシートを活用!
- 100均で蒸し布が手に入らない場合、クッキングシートを敷くことで食材がくっつくのを防げます。
- 蒸した後、蓋を少し開けて水滴を飛ばすと仕上がりが綺麗に!
- 蒸し終わった直後は、蓋の裏についた水滴が食材に落ちてしまうことがあります。余熱でしばらく乾かすことで、ベチャっとならずに仕上がります。
知るともっと楽しくなる!せいろ蒸しの豆知識
せいろを使うときに知っておくと役立つ知識をご紹介します。
- 木製せいろの「アロマ効果」
- せいろは木の香りがほんのり食材に移るため、蒸し料理の風味が増します。特にヒノキや杉のせいろは、香りを楽しめるのが特徴です。
- 蒸すだけで食材の甘みがアップ!
- せいろで蒸すと、じっくり熱が入るため、かぼちゃやさつまいもなどの甘みがより引き出されます。
- 蒸し時間を変えるだけで食感の違いを楽しめる
- 例えば、ブロッコリーは短めに蒸すとシャキシャキ、長めに蒸すとホクホク食感に。せいろなら微調整がしやすいので、好みに合わせられます。
これをやると失敗する?せいろ蒸しのNGポイント
せいろをうまく使いこなすために、やってはいけないポイントもチェックしておきましょう。
- 直火にかけると焦げる!
- せいろは鍋の上に乗せて使うものなので、直火にかけると焦げたり変形する原因になります。
- せいろの蓋をすぐに開けると温度が下がる!
- 蒸し途中で何度も蓋を開けると、温度が下がり加熱が不均一になります。様子を見るときは、できるだけ短時間で!
- 食材の並べ方を間違えると均等に蒸せない!
- かたい食材(にんじん、じゃがいも)は中央に、火が通りやすい食材(葉物、豆腐)は外側に置くとムラなく仕上がります。
せいろ蒸し料理は、食材をせいろ(蒸し器)に入れて蒸すだけのシンプルな調理方法ですが、その魅力は奥深いものがあります。
- ヘルシーで栄養価が高い:油を使わず調理できるため、カロリー控えめで栄養素をしっかり保持できます。
- 素材の旨みを引き出す:蒸すことで食材本来の味が引き立ち、特に野菜や魚介類は旨味が増します。
- 簡単&時短:食材を並べて火にかけるだけで完成するので、忙しい人にもぴったり。
せいろの選び方と使い方
せいろには様々な種類があり、用途に応じた選び方が重要です。
- サイズ:家庭で使うなら15cm~18cmの小型サイズが便利。
- 素材:竹製や木製のせいろは、蒸気を適度に調整しながら蒸せるため、食材の風味が引き立ちます。
- 段数:1段のせいろは単品調理向け、2段以上なら主菜と副菜を同時に蒸せて時短に。
野菜ごとの蒸し時間 & 下ごしらえ
せいろで蒸すと、食材の甘みや旨みが引き立ちますが、野菜ごとに適した蒸し時間を知ることが大切です。
| 野菜 | 蒸し時間 | 下ごしらえ |
|---|---|---|
| にんじん・じゃがいも | 10~15分 | 薄切りにすると時短 |
| ブロッコリー・カリフラワー | 5~7分 | 軽く塩をふると甘みが増す |
| ほうれん草・小松菜 | 2~3分 | サッと蒸して冷水に取る |
✅ 下ごしらえのポイント
- 大きめにカットすると食感が残りやすい。
- 少し塩を振って蒸すと、味が引き締まる。
100均蒸し板の耐久性と注意点【実際に使ったレビュー】
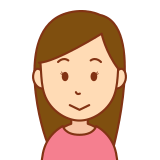
実際に何度か使ってみると、「ちょっとグラつく」「サイズが微妙に合わない」など、使いづらさが気になる場面もありました。
そんなときに試してよかったのが、市販の蒸し板セット。
【👉 本格的に使うならこの蒸し板セットが安心です】
※レビューでも「長く使える」「鍋にぴったりフィット」と評価されている人気商品です。
実際にセリアで購入した100均の蒸し板を何度か使ってみました。最初は「これで十分じゃない?」と感じたのですが、何度か使ううちにいくつか気になる点が出てきました。
まず、耐久性に関しては、水分や蒸気に触れる回数が増えると錆びやすくなる傾向がありました。とくに乾かすのが遅れると、素材が劣化しやすいです。また、せいろのサイズによっては、蒸し板が鍋の中でうまく固定されず、加熱中に浮いてズレてしまうこともありました。
軽さゆえに扱いやすい反面、安定感や熱伝導性に不安が残る場面もあります。頻繁に使う方やしっかりと料理をしたい方にとっては、もう少し丈夫なタイプを検討するのもひとつの手かもしれません。使い方次第で長持ちする場合もあるので、丁寧に扱うことがポイントです。
せいろを使った簡単レシピ
おすすめレシピ
1. 彩り野菜のヘルシー蒸し
- にんじん、ブロッコリー、パプリカなどをカット。
- せいろに並べて5~7分蒸す。
- オリーブオイルと塩でシンプルに味付け。
2. せいろで作るふわふわ蒸し卵
- 卵を溶きほぐし、だし汁と混ぜる。
- 器に入れて、せいろで約10分蒸す。
- お好みでネギやゴマを散らす。
3. せいろ蒸し肉まん
- 市販の冷凍肉まんをせいろで10分蒸すだけ!
- しっとりふわふわの仕上がりに。
せいろの調理時間と蒸し方のコツ
- 最適な蒸し温度・時間
- 弱火 → じっくり火が通るが時間がかかる。
- 強火 → 早く蒸せるが、焦げ付きやすいので注意。
- 段数ごとの使い分け
- 1段せいろ → 単品の調理向け。
- 2段せいろ → 主菜・副菜を同時に調理できる。
せいろ蒸しの失敗例と対策
せいろを使いこなすために、よくある失敗例と対策を紹介します。
- 水が少なくて焦げる!
- せいろを置く鍋の水が少ないと、蒸気不足で焦げ付きの原因に。しっかり水量を確保しましょう。
- せいろの蓋を頻繁に開けると温度が下がる!
- 蒸し途中で何度も開けると加熱が均一にならず、仕上がりにムラが出るため注意。
- 食材の配置ミスで均等に蒸せない!
- かたい野菜(にんじん、じゃがいも)は中央、葉物野菜(ほうれん草、小松菜)は外側に配置すると、均等に蒸しあがる。
せいろ蒸しをもっと楽しむアイテム
せいろ蒸しをさらに便利に、おしゃれに楽しむための100均アイテムも活用しましょう。
- 蒸し布(食材がくっつくのを防ぐ)
- 小さめの竹トング(取り出しやすい&おしゃれ)
- スパイス&調味料(塩レモン、ハーブソルトで洋風蒸し)
- カフェ風小皿(おしゃれな盛り付けに)
ちゃんと使いたい人におすすめ!100均以外の蒸し板3選
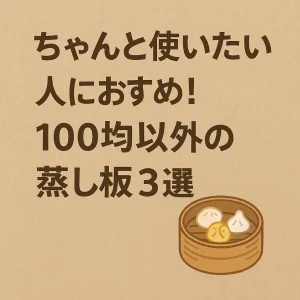
「100均でも試してみたけど、なんか安定しない…」「せっかくのせいろ料理だから、ちゃんとした道具で失敗したくない」——そんなふうに感じたことがある方には、しっかり使える蒸し板を選ぶという選択がおすすめです。
ここでは、実際に筆者が調べて「これは間違いない」と感じた蒸し板を3つ紹介します。ポイントは、鍋とのサイズ感・安定性・耐久性。そして、毎回の調理がストレスにならないかという実用面です。
100均に比べると価格は少し上がりますが、長く使うなら結局コスパがいいのはこっちかもしれません。
読者さんの「せいろライフ」がもっと快適になるように、人気・評価・実用性のバランスで選びました。
✅ 1. パール金属 木製蒸し板(26cm)
しっかりした厚みがあり、鍋との段差が少なく安定感バツグン。
天然木で作られており、せいろとの相性もよく、蒸気漏れも少なめ。レビューでも「最初からこれにしておけばよかった」という声が多く見られます。
🔸おすすめな人:市販のせいろとサイズが合わず困っている方

せいろ用プレート 26〜28cm 中華家 蒸し板 ( せいろ用受け台 蒸籠用受け台 受け台 中華セイロ用受け台 アルミ製 せいろを置く台 蒸し器替わり アルマイト加工 焦げ付き防止 時短 簡単 蒸し料理 蒸し調理 飲茶 )【3980円以上送料無料】
✅ 2. ステンレス製の汎用蒸し板(底が滑りにくい仕様)
水洗いしやすく衛生面でも安心。底が滑り止め仕様になっており、「蒸し器が動いてしまう」などの小さなストレスも回避できます。
🔸おすすめな人:日常的に蒸し料理をしたい方・頻度が高い方

Aieve せいろ 受け台 蒸し板 せいろ 蒸し器 ステンレス 15cm大内径 16~25cm蒸籠用 3段 階段式 20-24-27cm鍋 フライパン対応 中華セイロ受け台 蒸し料理
✅ 3. 和平フレイズ 鍋用蒸し台(15~26cm対応)
サイズ調整ができる可変型タイプで、複数の鍋に対応できる柔軟さが魅力。
100均だと鍋のサイズに合わなくて困ることが多いですが、これはその悩みを解消してくれます。
🔸おすすめな人:いろんな鍋を使い分けている方/せいろ初心者にも安心

送料無料 和平フレイズ EM-032 燕三 IH着脱式鍋4点セット(蒸し台付)
まとめ
せいろ蒸しは、簡単でヘルシーな調理方法であり、日常の食事に取り入れやすいものです。
- ヘルシーで美味しく、栄養価が高い
- 時短レシピにも活用できる
- 100均アイテムで手軽に始められる
セリアの蒸し板についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
→ 100均でも蒸し料理!セリアの蒸し板はせいろ代用になる?実践レビュー
100均の蒸し調理グッズ
煮込み料理に使えるスパイス特集

同じセリアのグッズでも、**お弁当や遠足にぴったりの「おしぼりケース」**が話題なのをご存知ですか?
→ 春の新生活に向けて「プチプラ×使いやすさ」で人気上昇中のアイテムをチェック!
子育て世代に人気!セリアのおしぼりケースが注目されている理由はこちら
2025年、セリアのおしぼりケースが子供におすすめな理由

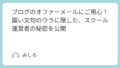
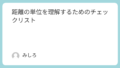
コメント