【18電話番号に出たらどうなる?そのリスクとは】
最近、18番号からの着信に「どうしても気になる」「なんだか恐いけど、出てもいいの?」と思ったことはありませんか?
この「18」で始まる電話番号。実はこれ、すべての人が必ずしも知っておいたほうがいい『要注意番号』の一つなんです。
一見「公式な感じ」を受ける数字列なので、最初は何の7590?と感じる人もいるはず。
しかしこの18番号、その裏側に隠れている事実はそんな甘くはありません。
この記事では、18番号に出た際のリスク、そしてそもそも出てもいいのかどうか。
そのポイントを、リアルな例を付けながら分かりやすく解説します。
18電話番号に関する基本情報
18から始まる電話番号とは?
「18」から始まる番号を見て、つい気になってしまうことはありませんか?実はこの番号、日本国内の一般的な電話番号とは異なり、国際電話に関連する番号の可能性があります。見慣れない「+18」「+181」などは、海外からかかってきたように見せかけるケースもあり、注意が必要です。特にスマホ画面に突然「18」で始まる番号が表示されると不安になる人も多いでしょう。
しかし、すべての「18」で始まる電話が危険というわけではありません。中には本当に海外からの正当な電話のこともあります。大事なのは、どの番号にどう対応するかを知っておくこと。この記事では、18電話番号の基本知識から、詐欺やリスクへの対応までを丁寧に解説していきます。
国際電話の仕組みと国番号
国際電話は、発信国の国番号をつけて発信されます。日本から海外へかける際は「010 + 国番号 + 相手先番号」となり、海外からかかってくる場合には「+国番号」で始まるのが一般的です。たとえば、アメリカなら「+1」、中国なら「+86」、韓国なら「+82」です。
つまり「+18」や「+181」といった番号も、実際には国番号の一部として表示されている場合があり、単なる市外局番や携帯番号とは異なります。しかし最近では、こうした国際電話の仕組みを逆手に取って、日本人が出やすい番号に偽装した詐欺電話が増えているのです。
そのため、電話番号の表示形式だけでは判断できないことが多く、出るか出ないかを迷ってしまうのも無理はありません。
総務省が教える18電話番号のリスク
実際に総務省も、**「国際電話番号を悪用した詐欺」**に対して注意喚起を行っています。特に「+81」「+181」「+1844」など、一見日本国内に見えるような表記で着信する電話は要注意です。
総務省の発表では、こういった番号からの着信に折り返し電話をかけると、高額な通話料が発生する可能性があると警告されています。これは、プレミアムチャージという仕組みを使って、一回の通話で数千円単位の請求が発生することもあるからです。
対策としては、まず「知らない番号には出ない」「折り返さない」「番号を検索する」ことが重要になります。スマホの着信履歴や通話アプリで番号を控え、怪しいと感じたらそのまま無視することが最も有効な防衛策です。
なぜ+181や+1844電話番号が危険なのか?
+181・+1844電話番号の特徴とリスク
これらの番号に共通するのは、日本人が安心して出てしまいそうな見た目をしていることです。「+181」は一見すると「+81」(日本)に見え、「+1844」は国内の市外局番「044」や「084」に近く、まぎらわしいのが特徴です。
実際には「+181」はアメリカの一部地域、「+1844」は北米のフリーダイヤル系番号として利用されています。しかし、日本人の感覚ではそのように認識されづらく、詐欺の温床となりやすいのです。
さらに、これらの番号は日本国内の事業者によってではなく、海外のコールセンターやスパム業者が悪用しているケースもあり、情報漏えいや金銭被害につながるリスクも指摘されています。
電話詐欺の手口と被害事例
被害の典型例として、「クレジットカードが不正利用された」「あなたの口座がロックされた」といった緊急性の高い内容で折り返しを誘導されるケースがあります。これに応じて折り返すと、待ち受けているのは高額請求。
また、AI音声を使って自動応答のように見せかける詐欺も増えています。リアルな声や抑揚があるため、つい信じてしまう人も少なくありません。
2024年には、こういった電話に対応してしまったことで、1回の通話で1万円以上の請求が発生した事例も報告されています。中には「数秒出ただけで…」といった驚きの証言もあり、被害の深刻さがうかがえます。
高額請求の可能性:注意が必要なケース
最も注意すべきなのは、「着信に出ただけでは料金は発生しない」と思い込んでいること。実際には、特定の国際電話網やプレミアム番号では、着信応答だけでも課金される仕組みが存在します。
特にプリペイドスマホや格安SIMなど、設定次第では海外料金が有効になってしまう環境では、リスクが高まります。さらに、キャリアによっては国際電話の受信料金が無料でないプランもあり、知らずに課金されていることも。
対策としては、スマホの「国際電話着信を拒否」設定や、迷惑電話対策アプリの導入、キャリアのサポート窓口に設定確認することが有効です。
迷惑電話対策と着信拒否方法
迷惑電話をブロックするアプリの活用法
スマートフォンの普及により、迷惑電話への対策も進化しています。現在では、着信時に相手の番号情報を自動で照合し、迷惑電話かどうかを判定するアプリが数多く存在します。代表的なアプリには「Whoscall」「電話帳ナビ」などがあり、ユーザーの評価や通報データをもとに警告を表示してくれます。
特に**「18」や「+181」などの不審な番号**からの着信が増えている今、こうしたアプリの導入は必須とも言える対策のひとつです。インストール後に自動で着信拒否設定ができるものもあり、普段の生活に大きな安心感をもたらします。
通信事業者による迷惑電話の対策
多くの通信キャリアでは、契約者向けに迷惑電話対策サービスを無料または低額で提供しています。NTTドコモ、au、ソフトバンクといった大手キャリアでは、専用オプションとして迷惑電話撃退機能が用意されています。
これらのサービスでは、迷惑電話がかかってきた際に自動で着信拒否したり、履歴から一括でブロック設定を行うことができます。また、特定の国際番号からの着信を制限することもできるため、「+18」や「+1844」などの不審な発信元を事前に排除できます。
家族を守るための着信拒否機能
高齢の家族やスマホに不慣れな子どもがいる家庭では、自分だけでなく家族全員を守るための設定が重要です。最近では、ファミリー向けのスマホやキッズケータイにも迷惑電話対策機能が搭載されており、保護者のスマホから遠隔で着信拒否設定を行うことも可能です。
特に「18」番号のように海外からの発信であっても、日本語で話しかけてくるケースがあるため、見慣れない番号は基本的に受け取らない設定にしておくことが安心です。
18電話番号の危険性とリスク管理
発信者の判断基準とその影響
電話番号の冒頭が「18」や「+181」「+1844」といった数字で始まる場合、それは海外からの発信であることを意味します。国際電話の形式では国番号が先頭につきますが、知らない国番号からの電話は基本的にリスクが伴います。
発信者が信頼できるかどうかを瞬時に判断するのは難しく、ワン切り詐欺やフィッシング詐欺の可能性もあります。少しでも不安を感じた場合は折り返し電話をせず、検索エンジンで番号を調べてみるのも有効な手段です。
不審なSMSの報告と対応方法
18番号や国際番号からの着信とセットで送られてくるのが不審なSMSメッセージです。本文に「荷物の不在通知」「口座確認」「動画リンク」などが記載されており、クリックを促す内容になっています。
このようなメッセージは、偽のサイトへ誘導し個人情報や金融情報を盗む目的で作られています。リンクは決して開かず、各キャリアや総務省が提供している迷惑SMS報告窓口に転送・通報することが推奨されます。
通話料の確認と危険な番号の特定
一部の海外発信電話は、高額な通話料が発生する仕組みになっています。数秒の通話でも数千円以上の料金がかかるケースもあり、ワン切りの折り返しを狙った詐欺に多く見られます。
通話明細をこまめにチェックすることで、身に覚えのない高額通話がないかを把握することができます。また、料金請求の明細に「国際電話」と記載されていたら、すぐに通信会社へ連絡し、ブロック設定や返金対応の相談を行いましょう。
実際の被害報告とその対策
実際の被害者による体験談
ネット上には、「+1844」や「+181」からの着信に応答したことで高額な請求が来たという報告が数多く見られます。中には、英語で急かすように話しかけてくるケースもあり、思わず応じてしまったという声もあります。
また、折り返した際に自動音声が流れるだけで通話料が加算されるという事例も存在します。こうした声からも、不審な番号には一切応答せず、即ブロック・通報する姿勢が大切であることがわかります。
警察と相談するべきケース
もし不審な電話やSMSに応答してしまい、実際に金銭被害が発生した場合は、警察への相談が必要です。最寄りの交番や警察署に相談すれば、被害届の提出やアドバイスを受けることができます。
さらに、サイバー犯罪対策課や消費者センターといった専門窓口も活用できます。「誰にも相談できない」「恥ずかしい」と思ってしまうかもしれませんが、早期対応が被害の拡大を防ぐ第一歩になります。
被害後の対処法と予防策
万が一、金銭被害や個人情報の漏洩が疑われる場合、まずは通信会社に連絡して通話履歴の確認と制限設定を行いましょう。次に、金融機関の口座情報やクレジットカードの利用履歴をチェックし、不審な動きがあれば速やかに凍結処置を依頼します。
また、今後の被害を防ぐためには、スマホに最新のセキュリティ対策アプリを導入し、家族や身近な人にも今回の体験を共有して注意を促すことが大切です。
まとめ:18電話番号のリスクと対策
知識がカギ!危険を回避する方法
18から始まる電話番号は、国際電話の一部として使われることがあり、一般的には日本国内の番号とは異なります。このような番号に無防備に出ると、通話料の発生や詐欺被害のリスクが生じることもあります。重要なのは、こうした番号について基本的な知識を持つことです。見知らぬ番号からの着信に即座に応答せず、番号を調べてから対応する習慣をつけることが、自分自身を守る第一歩になります。
今後の対策と注意点
一度でも怪しい番号に出てしまった場合は、通話記録や請求履歴を早めに確認し、必要であれば通信会社や消費生活センターに相談することが大切です。また、迷惑電話ブロックアプリや携帯キャリアの提供する迷惑電話対策機能を活用するのも有効です。特に、高齢の家族がいるご家庭では、日常的に情報を共有しながら、どんな電話に出るべきかの判断力を育てていくことが安心につながります。
信頼できる情報源の活用法
ネットには様々な情報が飛び交っているため、正しい判断をするには信頼できる情報源の活用が重要です。総務省の公式ページや、各通信事業者のサポート情報、口コミサイトなどを確認し、具体的な被害事例や番号リストを把握しておくことで、より冷静に対応できます。曖昧な情報に惑わされず、一次情報を参考にする姿勢が、自分や家族を守る手助けとなるでしょう。
もっと知りたくなったあなたへ
18電話番号に関する情報は年々更新されています。気になったことはそのままにせず、身近な人と話し合ったり、調べたりすることで理解が深まります。不安を抱えたままにせず、今回の記事があなたの「気づき」や「安心」につながれば嬉しいです。誰かにシェアすることも、大切な一歩になるかもしれません。
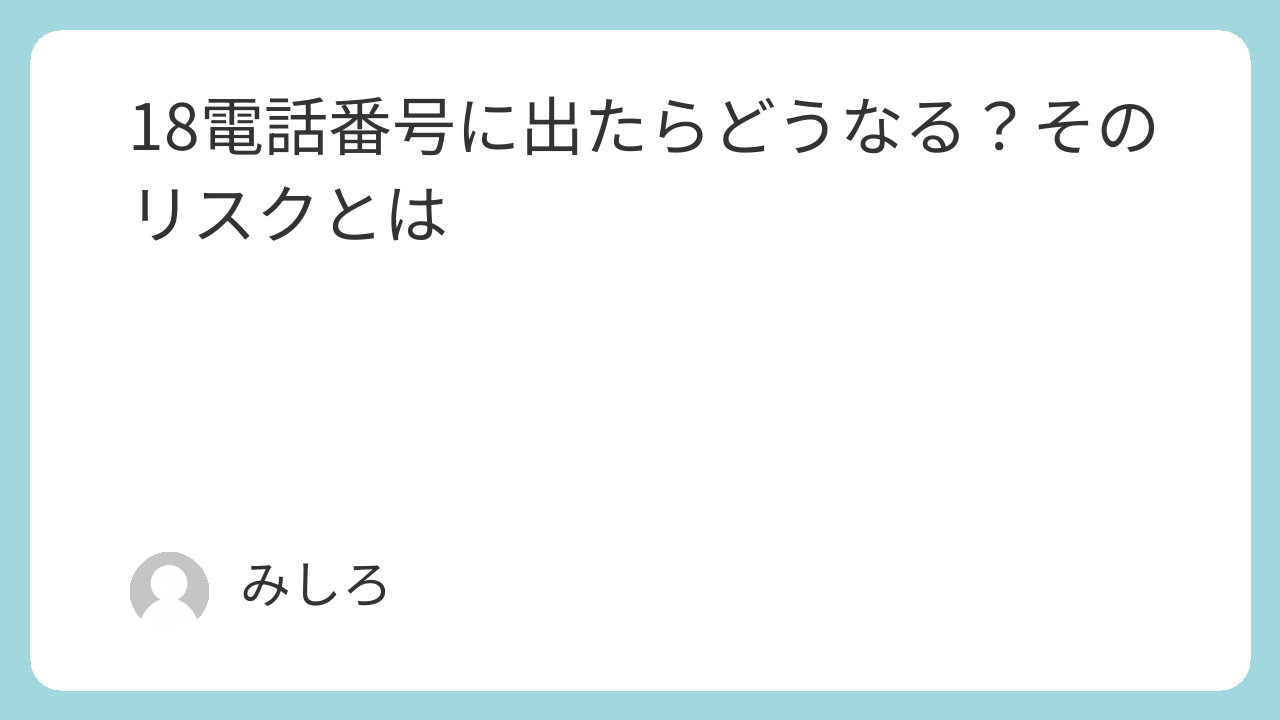
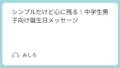
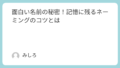
コメント