「コミュニケーションを図る」という表現、日常生活やビジネスシーンでもよく目にするようになりました。しかし、この表現が文法的に正しいのかどうか、不安に思ったことはありませんか?
この記事では、「コミュニケーションを図る」という表現が、日本語として正しいのか、その意味や使い方、類語までを徹底解説します。文習や言葉の意味を正しく理解しておくことは、会話でも、文書でも自信を持って表現するために大切な解釈力に繋がります。
文法・言葉表現を見直したい方や、正しく言葉を使いたい方は、この記事を通して一度しっかり見直していきましょう。
コミュニケーションを図るとは?
コミュニケーションの基本概念と重要性
人と人との関係において、コミュニケーションは空気のように欠かせない存在です。言葉や態度、表情などを通じて、思いや考えを伝えるこの行為は、信頼関係を築いたり、誤解を防いだりするうえで非常に重要な役割を担っています。現代社会では、対面だけでなくSNSやメールといった非対面型の手段も活発になり、ますますその重要性が増していると言えるでしょう。
「コミュニケーションを図る」の意味とは
「コミュニケーションを図る」とは、単に会話をするという意味にとどまりません。意図的に、相手と良好な関係を築こうとする働きかけを指します。ここでの「図る」は、「計画して試みる」「目的に向けて工夫する」といったニュアンスが含まれており、自然発生的なやりとりとは異なる、能動的な姿勢が求められる表現です。
コミュニケーションを図るととるの違い
似たような言い回しに「コミュニケーションをとる」がありますが、この二つには微妙な違いがあります。「とる」は行動に焦点があり、実際にやりとりすることを指します。一方「図る」は、まだ関係性ができていない状態で、積極的に関係構築を試みる段階で使われます。そのため、場面や目的に応じて使い分けると、より適切な表現になります。
職場におけるコミュニケーションの重要性
円滑な意思疎通のための方法
職場では、目の前の仕事だけでなく、周囲との連携が業務全体の効率を左右します。そのためには、単なる会話の回数ではなく、内容の質や相手への配慮がカギになります。例えば、定例ミーティングでの発言や日報での共有、オンラインチャットでの気軽な声かけなど、小さな積み重ねが大切です。意識的に「図る」ことを意識すると、コミュニケーションの質が大きく変わってきます。
社員間の信頼関係を築くために
仕事においては、信頼関係こそが土台になります。その構築のために欠かせないのが、日々のコミュニケーションです。特に新しいチームメンバーや他部署の人との関係においては、積極的に「コミュニケーションを図る」姿勢が重要です。何気ない雑談や、感謝の言葉を伝えるだけでも、距離が縮まりやすくなります。
例文で学ぶ!実際の使い方
最後に、「コミュニケーションを図る」の実際の使用例をいくつかご紹介します。
- 新しいプロジェクトに向けて、関係部署と積極的にコミュニケーションを図る必要がある。
- チームの雰囲気がぎくしゃくしているので、まずはメンバーとのコミュニケーションを図ってみようと思う。
- 異動してきたばかりなので、職場に早く馴染めるよう、コミュニケーションを図る努力をしている。
このように、単なる会話以上の「目的意識をもったやりとり」であることが、この表現の特徴です。
コミュニケーションを図るための具体的な方法
積極的にコミュニケーションを図る技術
相手との信頼関係を築くには、まず自分から話しかける姿勢が大切です。特に初対面やあまり話したことのない人と関わるときは、「挨拶+ひとこと」が有効。たとえば「お疲れさまです。今日の会議、分かりやすかったですね」と話しかけるだけでも、相手に安心感を与えることができます。さらに、相手の話をしっかり聞き、適度にうなずくことで、「話しやすい人だな」と感じてもらえる可能性が高まります。
会話が続かないときは、相手の発言を繰り返して「○○なんですね」と返すオウム返しも有効です。これにより、相手は話の内容に共感してもらえたと感じ、心の距離が近づいていきます。
効果的な情報共有の手法
コミュニケーションには、「気持ち」だけでなく「情報」も重要です。職場などのチーム内では、伝える内容を整理してから話すことが求められます。たとえば「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうした」という5W1Hに沿って話すと、相手に誤解を与えずに済みます。
さらに、メールやチャットなど文章での情報共有も増えていますが、書く前に「相手が読みやすいか」を想像する意識を持つことで、伝わり方が格段に良くなります。誤解を防ぐ一言を添えるだけでも、コミュニケーションの質は高まります。
相手の興味を引く表現と態度
「伝える」だけでは不十分で、「伝わる」ことが大事。そのためには、相手の立場や関心に寄り添った言い回しが必要です。たとえば、ITに詳しくない人に専門用語を使うと、聞き手は話についていけず、関係が一気に冷めてしまいます。
一方、相手が好きな話題や関心のある分野に言及すると、自然に会話が盛り上がりやすくなります。態度としても、表情・声のトーン・姿勢に気を配ることで、「話していて心地いい」と思ってもらえる効果があります。こうした細かな気遣いが、信頼の積み重ねにつながっていきます。
コミュニケーションを深めるための自己開示
自己開示の重要性と影響
「心を開いてもらいたいなら、まず自分から開く」。これはコミュニケーションにおける基本姿勢のひとつです。自己開示とは、自分の考えや感情、経験などを言葉で相手に伝える行動を指します。たとえば、「自分もその場面で悩んだことがあって……」と打ち明けることで、相手の共感を呼び、距離が縮まります。
もちろん、いきなり深い話をする必要はありません。軽めの雑談や失敗談から始めて、徐々に相手との関係を深めていくのがポイントです。自己開示は、誠実さや親しみやすさを伝える強力なツールとなります。
職場での自己開示の具体例
ビジネスの場面でも、適度な自己開示は効果的です。たとえば「自分も新人のころ、○○に悩みました」「そのやり方、私も最近試してみたんです」といった形で、自分の経験を語ると、相手の緊張が和らぎます。
注意したいのは、自慢話にならないようにすること。相手が話しやすい雰囲気を作るために、あくまで「共有する」姿勢で臨むことが大切です。こうしたやりとりが続くことで、「この人には安心して話せる」と思ってもらえる土台が築かれていきます。
「コミュニケーションを図る」の言い換え表現
類語や代替表現の紹介
「コミュニケーションを図る」という表現には、いくつかの言い換えが存在します。たとえば:
- 意思疎通をはかる
- 連携を強める
- 情報共有を進める
- 対話を重ねる
- 理解を深める
どれも「ただ話す」だけではなく、「関係性を築く」意図を含んでいます。文章や会話のなかで状況に応じて表現を使い分けることで、伝えたいニュアンスがより正確に伝わるようになります。
シチュエーションに応じた使い分け
言葉は状況によってふさわしい使い方があります。たとえば、社内会議であれば「情報共有を進める」「連携を強める」などが適しています。一方、上司とのやりとりで「意思疎通を図る」、同僚との雑談では「対話を重ねる」など、場面や相手に応じた自然な表現を心がけると、違和感のない印象を与えられます。
また、プレゼン資料やメール文で使う際は、少し堅めの言い回しにすることで信頼性や丁寧さも高まります。適切な言い換えは、あなたの伝えたいメッセージをより深く、広く届けてくれます。
日本語における「コミュニケーション」の漢字事情
「図る」と「はかる」の使い分け
日本語には同じ音でも意味が異なる漢字が多く、「はかる」もそのひとつです。「図る」「測る」「計る」「諮る」などがありますが、「コミュニケーションを図る」の場合は「図る」が正しいとされています。これは、計画的に進める、工夫する、意図するという意味があり、人との意思疎通を意識的に行おうとするニュアンスにマッチするからです。
一方で、「測る」や「計る」は数値や量を扱う場面で使われ、「諮る」は相談する場面で使用されます。ビジネス文書では、誤用が信頼性を下げるリスクもあるため、正しい使い分けを意識したいところです。
ビジネスシーンにおける漢字の重要性
職場で使われる文書やメールでは、読みやすさや正確さだけでなく、丁寧さや配慮も問われます。「コミュニケーションを図る」という表現も、正しく使えば相手への誠意や真剣さが伝わりやすくなります。
たとえば、企画書の中で「関係者との信頼関係を築くため、積極的にコミュニケーションを図る」とあれば、読み手に安心感を与えられます。小さな表現の積み重ねが、ビジネス上の信頼構築に直結するのです。
コミュニケーション能力向上のためのトレーニング
効果的な練習方法
コミュニケーション能力を鍛えるには、実践と客観視の両輪が欠かせません。例えば、簡単な日記をつけて、その日に交わした会話を振り返る方法があります。「なぜ伝わらなかったのか」「どう返せば良かったか」を自問するだけでも、意識は高まります。
また、会話を録音してあとで聞き返すのも有効。自分の口調や間の取り方を見直すことで、改善の糸口が見えてきます。
フィードバックの方法と重要性
自分一人での練習では限界があるため、他者からのフィードバックも積極的に受け入れましょう。信頼できる相手に「伝わりやすかったか」「共感できたか」など、具体的に意見をもらうことで、自分では気づかなかった癖や改善点が見つかります。
社内でロールプレイを取り入れたり、プレゼン練習後に感想を集める習慣も、スキル向上に役立ちます。
実践を通じたスキル向上の秘訣
最も効果的なのは「とにかく使ってみること」。挨拶や雑談、会議での発言、SNS投稿など、どんな場面でも意識的に言葉を選び、相手の反応を観察することがトレーニングになります。
失敗しても、そこから学べるのがコミュニケーション。場数を踏むことで、自然なやりとりができるようになります。
コミュニケーションに関するよくある質問(FAQ)
Q&A形式で解説する疑問点
Q:「図る」は口語でも使っていいの? A:ビジネスシーンでは定番表現ですが、日常会話ではやや堅めの印象を持たれることも。「話す」「やりとりする」など自然な言い換えも覚えておくと便利です。
Q:「図る」は間違っているという声もある? A:「図る=測る」と混同している人から誤解されるケースもありますが、文法的には誤りではなく、文脈次第で違和感が出るだけです。
英語での表現、コミュニケーションはどう伝える?
「コミュニケーションを図る」は英語で言うと “make an effort to communicate” や “facilitate communication” などが適切です。単に “communicate” だけでは、意図的に図っているニュアンスが伝わりにくくなります。
また、”build rapport”(信頼関係を築く)という表現も、ビジネスではよく使われます。状況に応じて表現を使い分けることが大切です。
まとめ:コミュニケーションを図ることの本質
信頼関係の構築と仕事の向上に向けて
「コミュニケーションを図る」という行為の根本には、信頼関係を築こうとする姿勢があります。一方的に伝えるのではなく、相手の立場に立ち、言葉を選び、伝わる工夫をすることが何より大切です。
職場では、円滑な連携やトラブル防止にもつながります。良好なコミュニケーションは、仕事の質やスピードにも確実に影響してくるでしょう。
日常生活での実践の重要性
コミュニケーション力は特別な技術ではなく、日々の中で少しずつ磨かれるもの。家庭での会話や、店員さんとのやり取り、友人との雑談──そうした日常の積み重ねが、いざという場面での力になります。
難しく考えすぎず、まずは「相手に興味を持つこと」から始めてみましょう。
もっと知りたくなったあなたへ
「伝えたいことが伝わらない」「相手との距離感がつかめない」と感じたら、まずは自分の言葉に意識を向けてみてください。
実は、言葉の選び方ひとつで、伝わり方はまったく変わります。この記事が、あなたの「伝える力」をもう一段階深めるヒントになれば嬉しいです。
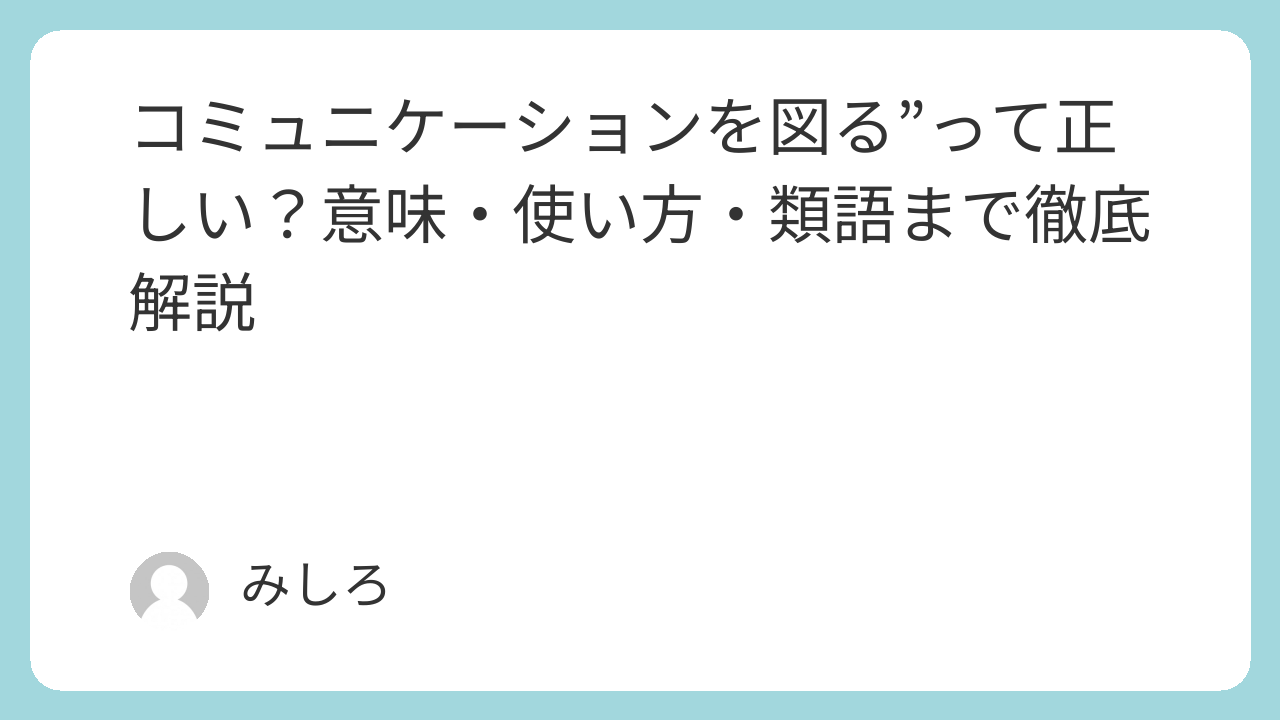

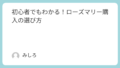
コメント